〜〜なんでも、いろいろ日記 2015〜〜
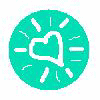 Starting flom within
Starting flom within
カウンセリングに関することや気づいたことを綴ります
12/22/2015
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
2015年 1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月
| 2015年12月16日(水) | |
| グループ「アロー」勉強会(共依存症②) | |
今日のセルフヘルプグループ「アロー」の活動は、2週間前に引き続き 共依存症の勉強を取り入れ、行いました。 テーマ : 『共依存症からの回復』 ・共依存症の特徴 ・回復するには・・・ ・自分で出来る行動療法(実践法) 終了後、参加メンバーに「共依存」について思ったことを話してもらいました。 自分の共依存的部分を考えてみたり、家族関係や職場での対人関係を振り返る様子がうかがえました。 今までの、自分の考え方の癖や、行動パターンを変えるのはなかなか難しいことだと思います。 最初はうまくいかなくても、うまくいった点やチャレンジしていることに目を向け、繰り返し実践していってほしいものです。 もしも、うまくいかなくてもグループに訪れ、チャレンジした体験をメンバーに話してください。 聴かせてください。 一緒に考えていきましょう。。。 |
Wishing your family peace and love at Christmas and alwaus.  ===富山にて=== 研修時、街で見かけた クリスマスツリー |
| 2015年12月5日(土) | |
| 勉強会(認知行動療法Ⅱ) | |
認知行動療法(CTB)の勉強会に参加しました。 認知には2種類あります ・自動思考・・・日常生活で自然にパッと浮かんでくる考えやイメージ ・スキーマ・・・心の中にある自分が身につけてきた考え方や価値観や道徳観 たとえば、男は泣いちゃいけないとか頼まれたことは断ってはいけないなど。 基本プロセスは、起ったこと、出来事をどう捉えるか共に継続し、確認していくことです。 ①自分で自分を観察する力をつける ②良いところも良くないところもある現実を、ありのままみて、どんな事実があるのか捉えられるようにする ③現在の状況で何が変えられるのか、何をどうすればいいのか、みえてくる 辛くて辛くてしょうがない時や、自分が何を感じているのか自分の感情が分からない時、又は感情が爆発しそうな時は、感情を一旦外に置いて、「どうすると楽になるか?」対処の方法に焦点をあてましょう。 あなたにとってのより良い方法を共にみつけていきましょう。。。カウンセリングルーム「フロー」 |
| 2015年12月2日(水) | |
| グループ「アロー」勉強会(共依存症①) | |
セルフヘルプグループ(自助グループ)「アロー」のミーティングでは、機能不全な家族の中で受けた心の傷とは別に、職場や日常の生活で、どうも相手との関係がうまくいかない。という話しになることもしばしばあります。 そこで、今日は、学術的病名ではないけれど、自分のことを置き去りにして相手のために自分を見失ってしまう症状「共依存症」の勉強を取り入れ、オープンミーティング形式で行いました。 テーマ : 『共依存症について』 ・依存症と共依存症 ・一次症状(5つの障害) ・二次症状(5つの態度) ・セルフチェック 12月16日(水曜)13:30からは第2回目として『共依存症からの回復』をテーマに行います。 対人関係のヒントとなるような内容にしたいと思っております。 |
| 2015年11月29日(日) |
| 講演会(交流分析) |
今日は、交流分析北陸支部の年次大会に参加しました。 テーマ : 『心の問題解決にやさしい交流分析』 講 師 : 江花 昭一 先生 神奈川大学保健管理センター長(産業医・学校医・特別教授) 4人家族のやり取りの例を参考に、TA(交流分析)の4つの分析と3つの理論では、どう考えるか。 どう改善すれば、効果的な交流ができるか。 また、不登校の中学生A君のカウンセリングの例、解決思考の対話法のプロセスをご紹介くださいました。 認知行動療法、グリーフセラピーと共通する部分が多く、なるほどなぁと思いながら拝聴しました。 心の問題について、、、 実は「心」の問題ではないことが多い。 「心」が個人を支配しているのではなく、個人が「心」を使って交流している。。。。 交流分析では、人を「交流している個人」と考え、交流している人をみる。 心をみているのではない。 と・・・このあたりは、うまく理解できず私自身落とし込むことが出来ませんでした^^;;; なんとなくこうなのかな?こう考えればいいのかな? との思いはありますが、 これから経験したり勉強するうちに理解できるようになるのでしょうか? 課題としてとっておくことにしました。マル 午後からは、会員の体験発表の分科会(教育・家庭・地域)に参加しました。 ● 親子のコミュニケーションにTAを使って〜事例報告〜 ● 「泣いた!笑った!紙芝居作りに挑戦 思いは叶う!」 〜本当だ!心(感情)の使い方でパフォーマンスは変化する〜 ● 初めて「TA 子育ち支援講座」を開催してみて |
| 2015年11月27日(金) |
| 勉強会(認知行動療法Ⅰ) |
今夜は認知行動療法(CBT)の背景にある考え方や日常に使えそうな技法、自己理解に役立つワークを交えての勉強会に参加しました。 まず、精神科で行われている認知行動療法の目指すところや、面接の進め方を学んだうえで・・・起った事(出来事)をどう捉えているか(認知)、自分の考え方のクセを知り、そのメリットやデメリットを考えるワークをしました。 考え方のクセは、誰にでもあるもの。。。 例えば、「○○すべき!」のようにべき思考(一つの基準を重要視するクセ)が強い場合 メリットは、規則を守る、道徳心,向上心が強いなど デメリットは、基準を外れると批判的に思う、否定的に感じるなど 良いところもあれば、良くないところもありますが、クセが自分の辛さや苦しさにつながっていたり、極端な場合は考え方を見直していきましょう。。。 |
| 2015年10月25日(日) |
| 講演会(発達障害) |
『発達障害』と呼ばれる状態を持つ子どもたちが、より良い生活を過ごすには、 周囲の方々の正しい理解と対応がとても大切です。 「どうして自分だけが周りの人と同じことができないんだろう・・・それは自分がダメだから」 と自分を責め、家族と衝突してきた日々。 大人になり、広汎性発達障害(今は「自閉スペクトラム症」という)と診断されてから 自身を受け入れられるようになった。 というケースなどをお聴きするに考えさせられます。 今日は、発達障害(主にASDとADHD)の講義を受けてきました。 テーマ : 『発達障害の状態にある子どもの理解と支援』 〜特性と障害状態を分けて考えましょう〜 講 師 : 宮本 信也 氏 筑波大学特別支援教育研究センター長 <ピックアップ> 発達障害 社会との関連性の中で生じる・・・病気ではなく、困難を生じやすい 本人が苦手な事に「がんばれ」となる・・・「がんばれ」よりも手助け 「非定型発達特性」は「障害」ではない その特性を背景として生じている生活上の困難やトラブルが問題。これが「障害の状態」 「障害の状態」は支援により変えられる 困った子どもではなく、困っている子ども 苦手なことを全て一人でできるようになる知識やスキルを支援することではなく、 苦手部分をカバーするためのやり方や上手に助けを求められることを支援する Aさん : 「Did you have lunch ?」 (お昼ごはん食べましたか?) Bさん : 「No,I didn't.」 (お弁当は持ってきませんでした). Aさん : 「Let's go to lunch!」 (では、一緒に食べに行きましょう) Bさん : 「Yes let's!」 (行きましょう) このAさんとBさんのやり取りには何の問題もありませんが・・・ haveには持つという意味と食べると言う意味がありますよね。 ASD(自閉スペクトラム症)の人たちとの会話の落とし穴の例えです。 通じている、分かり合えているようで、実はお互い違う意味で理解していて、実は通じていない。 しかも、そのことに気づいていないという例えです。 アメリカ滞在経験の友人にこの話をすると、お弁当についてたずねる時はyour lunchとするか、a lunchbox と言うので、このような曖昧さは、ないかも・・・と 先生が、知能障害のないASDの特徴を話された中で、アメリカ文化でOKだけど、日本ではNGな部分、社会,文化,時代の違いで見方が変わってくると話されてたこと・・・こういうところなのかなぁと思えました。 障害に限らず、相手に関心を持つこと、相手を理解しようと思う気持ち、丁寧にゆっくりとをあらためて考える最近です。 |

| 2015年6月27日(土) |
| 講演拝聴(カウンセリングについて) |
今日は、パールズのゲシュタルト(全体性を感じながら気づく)、ロジャーズのカウンセリングの条件について拝聴しました。 テーマ : 『ゲシュタルト療法とカウンセリング』 イメージを使って五感に働きかけるワークを交えての講演でした。 毎年、参加する講演ですが、だまし絵を使ったワークでは、以前気づけたものが気づけなかったり、 イメージの中では昨年と違った『いま、ここ』での五感を感じたり、 自分のカウンセリング態度を振り返りながら自己理解の大切さをあらためて思いました |
| 2015年6月20日(土) |
| 講演拝聴(医学の基礎知識) |
今日は、精神科医師からみた 医師、医療、福祉の本質的問題や意味について、拝聴しました。 テーマ : 『簡単な精神医学の基礎知識』 西欧の医療と日本の医療の歴史的背景を比べ、精神医療が今日に至るまで、また、社会的問題点を盛り込んでのお話でした。 ロザリン・カーター(カーター大統領夫人)の言葉 精神病者がどのような処遇をされているかでその国の文化水準がわかる 精神障害者の差別、正常と異常、こころと身体について考えさせられました |
| 2015年5月10日(日) |
| 勉強会(交流分析入門講座) |
今日は、交流分析を知っていただくため仲間の方々が開いた入門講座へ、お手伝い兼自己点検のため講座に参加しました。 交流分析を知って、かれこれ10年以上経ちます。 コミュニケーションの改善や職場の活性化等多くの場面で活用されている心理学です。 『過去と他人は変えられない。変えられるのは‘今ここ’での自分だけ』という交流分析の理念を聞き、もっと勉強したいと思ったことを思い出します。 私にとっての交流分析は、自分を理解するため、気づくためのツールです。 カウンセラーの態度条件として自己一致していることがあげられますが、そもそも自分の考え方や感じ方の癖を知っていないと自己一致できないのではないでしょうか。 自分の先入観や感情や思考を一旦、心の器から取り出します。けれど、感情や思考は次々と生まれてきます。 が、「今、私は、相手を見ながら、話を聴きながら、こう感じた。こう思った。」ともう一人の自分が自分の状態を分かりながら相手とピュアに関わっていく・・・これが、難しいです。 主観的になっていないか?自分の思い込みで相手をみていないか?そう分かって発信しているか?などなど・・・点検します。 久しぶりのエゴグラムは、あまり変化はなかったけど、初心に戻り新鮮な勉強会になりました。 そして、仲間が普段見せない活き活きとした姿をみれて、うれしかったです。 自己理解,他者理解を深めたい・・・今よりも人との関係をよくしたい方へ 平成27年度 日本交流分析協会 北陸支部 講座スケジュール |

| 2015年3月17日(火) | |
| 勉強会(自助グループ交流会) | |
今夜は、「 アルコール,ギャンブル,薬物依存、その家族の会、アダルトチルドレンなどの自助グループと支援する方たちとの勉強会です。 7つのグループから一人ずつが自身の辛かったことや今のことや会についてを話します。 グループ「アロー」は昨年、一昨年に引き続き3度目の参加となりましたが、今回は話してみようというメンバーがいらっしゃらず、私が話しました。 内容、感想は後日、メンバーの声にアップするとして・・・ 交流の場では、幼少の頃からの自分史的なことを語られる方が多かったように感じました。 (一番最初にアダルトチルドレンとして私が発表した事が影響したのかな?と勝手に思う私ですが・・・^^;苦笑) 自身に起こった事を正直に、気持ちを誤魔化すことなく語る姿。 「自分は弱い人間です」と話すその姿がとても力強く感じ、その強さを目の当たりにし、人間って!生きるって!なんて壮絶なことなんだろうかと思いました。 お別れする時、NAの方から握手を求められ、互いに言葉は交わさずとも、真っ直ぐ目を見て握手したこと、忘れられません。うれしかったです。ありがとう。 この会を準備してくださった方々、毎年お誘いくださる先生、どうもありがとうございました。 |
==  昨年の今頃、 ひっそりとした山奥で みつけた花です 厳しい冬をしのぎ 根を張り 雪残る山に咲く花 誰かに見られることはなくても 今年も美しく 可憐に 咲いていることでしょう・・・ |
| 2015年2月22日(日) |
| 講演会拝聴(自閉症・発達障害) |
| テーマ : 自閉症スペクトラムのライフスタイル 〜長い人生を考えながら〜 講 師 : 志賀 利一 氏 のぞみ園 事業企画局研究部長 生まれてから高齢期にいたるまでの、長いスパンでみた成長に伴う親の視点や心理的変化、今後を考える生き方について、 中度の知的障害をともなう自閉症の方を仮想事例にしてのお話でした。 心身障害者の福祉の歴史について、1979年に養護学校が義務化となり、30年前には20歳からの障害基礎年金もなかったのだと聞きました。 障害の有無の格差が次第に小さくなるよう、私たちは差別や偏見をもたず、共に生きる者同士、理解しようとする気持ちが大切だなぁと思いました。 <ご案内下さった本> 障害のある子の家族が知っておきたい・・・「親なきあと」 渡部 伸 著 |